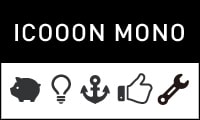【個人事業主必見】どこまで経費で落ちる?家賃・光熱費・飲食代など具体例で解説
- 2024.10.17
- 税金・法律

個人事業主やフリーランスとして活動する上で、最も重要かつ頭を悩ませるのが「経費」の管理ではないでしょうか。「この支払いは経費になるのだろうか?」「どこまで経費として計上していいのかわからない」といった疑問は、多くの方が一度は抱くものです。
経費を正しく理解し、漏れなく計上することは、手元に残るお金を最大化する、つまり「賢い節税」に直結します。しかし、その判断基準は意外と曖昧で、個人的な支出と事業用の支出の線引きに迷う場面も少なくありません。もし誤った判断で経費を計上してしまうと、税務調査で指摘され、後から追加で税金を支払うことになるリスクもあります。
この記事では、個人事業主・フリーランスの方々を対象に、経費の基本的な考え方から、家賃や飲食代といった具体的なケーススタディまで、どこまで経費として認められるのか、その境界線をわかりやすく解説します。正しい知識を身につけて、自信を持って確定申告に臨みましょう。
そもそも経費とは?基本的な考え方をマスターしよう
具体的な例を見る前に、まずは経費として認められるための大原則を理解しておくことが重要です。この原則さえ押さえておけば、様々なケースに応用が利くようになります。
経費として認められるための大原則
所得税法では、経費のことを「必要経費」と呼びます。そして、必要経費として認められるのは、「事業の総収入金額を得るために直接要した費用の額」と「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」と定められています。
少し難しい言葉ですが、これを簡単に言い換えると、「事業の売上を上げるために直接的、または間接的に必要な費用」が経費になる、ということです。この「事業関連性」こそが、経費を判断する上での絶対的な大原則となります。
逆に言えば、事業とは全く関係のない個人的な趣味や生活のための支出は、当然ながら経費にはなりません。
「これは経費?」迷ったときの判断基準
日々の支出の中で、「これは経費になるかな?」と迷ったときは、以下の3つの基準で自問自答してみてください。
- 基準1:その支出は、事業の売上につながるものか?
- 基準2:その支出が、事業に関係することを客観的に説明できるか?
- 基準3:その支出額は、社会通念上、妥当な金額か?
例えば、Webデザイナーがデザインの参考にするために購入した書籍代は、売上(良いデザインを作ること)につながるものであり、客観的な説明も可能です。しかし、個人的に楽しむための小説は経費にはなりません。また、取引先との1回のランチ代が10万円だった場合、社会通念上、妥当な金額とは言えず、税務署から説明を求められる可能性が高くなります。
この3つの基準を常に意識することが、適切な経費判断の第一歩です。
【具体例で解説】経費にできるもの・できないものの境界線
それでは、多くの人が判断に迷いがちな支出について、具体的な例を挙げながら経費にできるかどうかの境界線を解説していきます。
① 自宅兼事務所の費用(家事按分)
自宅を事務所としても利用している場合、家賃や水道光熱費などの一部を経費にできます。この、プライベート利用と事業利用が混在している費用を、事業で使った割合に応じて分ける会計処理を「家事按分(かじあんぶん)」と言います。
家賃・住宅ローン
家賃は、事業で使用している「面積」の割合で按分するのが一般的です。
(計算例)
家全体の面積が60㎡、そのうち仕事部屋が15㎡で、家賃が月12万円の場合
事業使用割合:15㎡ ÷ 60㎡ = 25%
経費にできる金額:12万円 × 25% = 月3万円
※持ち家の場合、建物部分の減価償却費、固定資産税、火災保険料、住宅ローンの金利部分が家事按分の対象になります。元本返済部分は経費になりません。
水道光熱費・通信費
電気代やインターネット代なども家事按分が可能です。これらは面積よりも、事業で使った「時間」の割合で計算する方が合理的とされています。
(計算例)
1週間のうち、平日5日間、1日8時間仕事をする場合
事業使用割合:(8時間 × 5日)÷(24時間 × 7日)≒ 23.8%
月の電気代が1万円なら、約2,380円が経費となります。
家事按分を行う際は、「なぜその割合にしたのか」という客観的で合理的な根拠を、税務署に説明できるようにしておくことが非常に重要です。
② 飲食代(接待交際費・会議費)
飲食代は、公私混同が起こりやすいため、税務調査でも厳しくチェックされるポイントです。誰と、何のために食事をしたのかが重要になります。
- 経費にできる飲食代
- 接待交際費:取引先との関係を円滑にするための会食や贈答品、お中元・お歳暮など。
- 会議費:取引先やスタッフとの打ち合わせの際のコーヒー代やお弁当代など。
- 情報収集のためのカフェ代:仕事に関連する情報収集や作業のためにカフェを利用した場合、その場所代としてコーヒー代を経費にできる場合があります。
- 経費にできない飲食代
- 一人でのランチや夕食代:事業主一人の食事代は、原則としてプライベートな生活費とみなされ、経費にはなりません。
- 家族や友人との食事代:事業に全く関係のない人との食事代は経費になりません。
飲食代の領収書には、「いつ、誰と(相手の会社名・氏名)、何人で、何のために」といった情報を裏面にメモしておく習慣をつけましょう。
③ 移動・出張に関する費用(旅費交通費)
打ち合わせのための移動や出張にかかる費用は、旅費交通費として経費になります。
- 電車、バス、タクシー、飛行機などの交通費
- 出張時のホテルなどの宿泊費
- コインパーキングなどの駐車場代
- 事業で使う自家用車のガソリン代、車検代、自動車税(これらも家事按分が必要)
SuicaやPASMOなどの交通系ICカードは、プライベート利用と混ざりがちです。事業用のカードを一枚用意するか、利用履歴をこまめに印刷して事業で使った分を明確に区別できるようにしておきましょう。
④ 仕事で使う道具・備品(消耗品費・減価償却費)
仕事で使うパソコンやデスク、文房具などももちろん経費になります。ただし、金額によって会計処理の方法が異なります。
- 10万円未満のもの:「消耗品費」として、購入した年に全額を経費にできます。(例:ボールペン、プリンターのインク、USBメモリなど)
- 10万円以上のもの:「減価償却費」として、法律で定められた耐用年数に応じて数年間に分割して経費に計上します。(例:パソコン(耐用年数4年)、普通自動車(耐用年数6年)など)
【青色申告者の特例】
青色申告を行っている場合、「少額減価償却資産の特例」を使えます。これにより、1個あたり30万円未満の資産であれば、購入した年に一括で経費に計上することが可能です(年間合計300万円まで)。これは大きな節税メリットなので、ぜひ活用しましょう。
⑤ スキルアップ・情報収集の費用
事業の遂行に直接必要な知識やスキルを得るための費用も経費になります。
- 新聞図書費:仕事に関連する書籍、専門誌、新聞、有料メルマガなどの購読料。
- 研修費:事業に関連するセミナー、研修、勉強会への参加費。
ただし、将来のための自己投資という側面が強い資格取得費用(例えば、Webデザイナーが全く関係のない不動産系の資格を取るなど)は、経費として認められない可能性が高いので注意が必要です。
経費計上で絶対にやるべきこと・注意点
正しい経費計上を行うためには、日々の管理が欠かせません。以下の3つのポイントを必ず実践しましょう。
① 領収書・レシートは必ず保管する
経費を計上するには、その支払いを証明する証拠書類が必要です。領収書やレシートは、経費の最も基本的な証拠となります。法律で保管期間が定められており、青色申告の場合は7年間、白色申告の場合は5年間の保管義務があります。月ごとに封筒やファイルにまとめて整理しておきましょう。万が一もらい忘れたり紛失したりした場合は、出金伝票を作成したり、クレジットカードの明細を保管したりして対応します。
② 帳簿に正しく記録する
確定申告では、日々の取引を記録した「帳簿」の作成が義務付けられています。領収書があるだけでは不十分で、その支出が「いつ、どこで、何のために、いくら」使われたのかを帳簿に記録する必要があります。手書きやExcelでの管理も可能ですが、近年はクラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード クラウドなど)を利用するのが主流です。簿記の知識が少なくても、効率的かつ正確に帳簿付けができます。
③ プライベートな支出と明確に分ける
個人事業主は、事業とプライベートのお金の区別が曖昧になりがちです。税務調査で最も指摘されやすいのが、この「公私混同」です。対策として、事業専用の銀行口座とクレジットカードを用意することを強くおすすめします。これにより、事業のお金の流れが一目瞭然となり、経費の管理が格段に楽になります。
まとめ:正しい経費計上が節税の第一歩
今回は、個人事業主・フリーランスにとって重要な「経費」について、基本的な考え方から具体的な判断例、管理の注意点までを解説しました。
経費を漏れなく計上することは、事業の利益を正確に把握し、納める税金を適正な金額に抑えるための基本中の基本です。日々の支出に対して「これは事業の売上を上げるために必要な支出か?」と自問自答する癖をつけることが、正しい経費判断の第一歩となります。
とはいえ、事業活動が多様化する中で、判断に迷うグレーなケースが出てくるのも事実です。もし経費の判断に迷ったり、より効果的な節税対策を知りたいと考えたりした際には、専門家である税理士に相談するのも一つの有効な手段です。専門家の視点からアドバイスを受けることで、安心して事業に集中できる環境を整えることができます。
-
前の記事

税理士を変更する際に、現在の顧問税理士にどう伝えれば良い? 2024.09.25
-
次の記事

【中小企業経営者向け】決算前に見直したい!今すぐできる王道の法人税節税策10選 2024.11.02