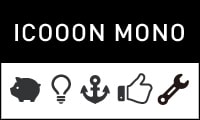法人税の仕組みとは?会社経営者が知っておきたい基本と計算方法
- 2025.09.15
- 税金・法律

会社を経営していると必ず関わることになるのが「法人税」です。法人税は、会社の利益に対して課される税金であり、経営者にとって避けては通れない重要なテーマです。しかし、法人税の仕組みや計算方法は複雑で、「どの部分に税金がかかるのか」「どんな控除が使えるのか」といった点が分かりにくいと感じる方も多いでしょう。この記事では、法人税の基本的な仕組みから、具体的な計算の流れ、経営者が知っておくべきポイントまでを解説します。
法人税とは何か?
法人税とは、株式会社や合同会社といった法人の所得(利益)に対して課される国税です。個人に課される所得税と同様に、法人が得た利益に対して課税される仕組みになっています。ただし、法人の場合は事業活動の規模や形態に応じて課税方式や税率が異なる点が特徴です。
法人税は国税であると同時に、法人事業税や法人住民税といった地方税と合わせて負担する必要があるため、総合的に「法人税等」と呼ばれることもあります。
法人税の課税対象となる所得
法人税がかかるのは「所得」、すなわち会社の利益です。ただし、ここでいう利益は会計上の利益と必ずしも一致するわけではありません。法人税の計算では、会計上の利益をベースにしながら、税法上のルールに基づいて調整が行われます。
法人税の課税所得は、次のように算出されます。
課税所得 = 益金(収益) – 損金(経費) ± 税務上の調整項目
益金とは、売上高や受取利息、雑収入など、会社が得た収益のことです。一方、損金とは、売上原価や人件費、家賃、水道光熱費、広告宣伝費など、事業を行う上で必要な経費を指します。
さらに、税務上は会計処理と異なる取り扱いがあるため、税務調整を行って最終的な課税所得を確定させます。
法人税の計算方法
法人税額は、以下の流れで計算されます。
- 1. 会計上の利益を算出
損益計算書の当期純利益がベースとなります。 - 2. 税務調整を行い課税所得を計算
会計上の利益から税務上認められない経費を加算したり、逆に税務上のみ認められる損金を差し引いたりして課税所得を算出します。 - 3. 税率を適用して法人税額を算出
課税所得に法人税率を掛けて法人税額を計算します。 - 4. 地方税を加算
法人税に加えて法人住民税や法人事業税などを加算し、最終的な納税額を確定します。
法人税率の目安
法人税率は所得金額や資本金規模によって異なります。中小企業に適用される法人税率の代表的なものは以下の通りです。
| 課税所得金額 | 法人税率(国税) |
|---|---|
| 年800万円以下 | 15%(軽減税率) |
| 年800万円超 | 23.2% |
この法人税額に加え、法人住民税や法人事業税などを考慮すると、実効税率(トータルの負担率)はおよそ30%前後になるケースが一般的です。
法人税の申告と納付の流れ
法人税の申告と納付は、原則として決算日から2か月以内に行わなければなりません。流れは次のようになります。
- 決算終了後、会計帳簿をもとに損益計算書・貸借対照表を作成
- 税務調整を行い、法人税申告書を作成
- 法人税・法人住民税・法人事業税を算出
- 所轄税務署および地方自治体に申告書を提出
- 納税期限までに法人税等を納付
期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税といったペナルティが発生するため、注意が必要です。
法人税に関する節税のポイント
法人税は会社の利益に対して課税されるため、適切な経費計上や制度の活用によって節税が可能です。経営者が押さえておきたい代表的なポイントを紹介します。
- 必要経費を漏れなく計上する
交際費、旅費交通費、消耗品費など、事業に関連する支出は正しく経費に計上することが重要です。 - 中小企業向けの各種制度を活用する
少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括経費計上)や中小企業投資促進税制など、特例措置を利用することで税負担を軽減できます。 - 役員報酬の設定を工夫する
役員報酬は損金算入できるため、会社と個人の所得をバランスよく分配することが節税につながります。 - 繰越欠損金の活用
赤字が出た場合、その欠損金を将来の黒字と相殺できる制度があります。中小企業であれば最大10年間繰り越すことが可能です。
法人税を正しく理解することの重要性
法人税は会社経営に直結する重要な要素です。税金の仕組みを理解していないと、無駄な納税や思わぬ追徴課税につながる恐れがあります。逆に、正しい知識を持ち、適切な経費処理や制度の活用を行うことで、会社の資金繰りを大きく改善できる可能性があります。
特に税務署からの調査に備えて、日頃から帳簿を整え、税理士と連携して適正な申告を心がけることが経営者に求められる姿勢です。
まとめ
法人税は会社の利益に課される国税であり、地方税と合わせて「法人税等」として負担する必要があります。課税所得の算出方法や法人税率の仕組みを理解しておくことは、経営者にとって不可欠です。
計算方法は複雑ですが、流れを押さえれば「利益に応じて課税される」という基本構造はシンプルです。また、経費の適切な計上や各種特例制度を活用することで、法人税の負担を軽減することが可能です。
会社経営を安定させるためには、法人税を正しく理解し、計画的に対策を行うことが欠かせません。税理士と連携しながら、適正かつ有利な申告を心がけることで、企業の成長につなげていきましょう。
-
前の記事

税務調査が来たらどうする?対象になりやすいケースと対応方法 2025.08.14
-
次の記事
記事がありません