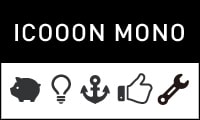暦年贈与と相続時精算課税制度、どっちがお得?2025年最新の税制改正ポイント
- 2025.06.20
- 税金・法律

はい、承知いたしました。
「暦年贈与と相続時精算課税制度、どっちがお得?2025年最新の税制改正ポイント」というテーマで、ご指定の要件に基づき記事を作成します。
リードテキスト
「子や孫の将来のために、早めに財産を渡しておきたい」
「でも、贈与税は高いと聞くし、どうすれば一番良いのだろう?」
「『暦年贈与』と『相続時精算課税制度』、結局どっちを選べばいいの?」
生前贈与は、相続対策の有効な手段の一つですが、その制度は複雑で、多くの方がこのような悩みを抱えています。特に、2024年1月1日からスタートした税制改正により、これまでの生前贈与の常識は大きく変わりました。以前は「暦年贈与が断然お得」と言われることが多かったのですが、今(2025年現在)はその優位性が揺らいでいます。
この記事では、2025年現在の最新のルールに基づき、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の仕組みと変更点を徹底比較します。「自分の場合は、どちらの制度を使うべきか」を判断するための具体的なケーススタディも交えながら、わかりやすく解説していきます。
まずは基本をおさらい!2つの贈与制度の仕組み
最新の改正ポイントを理解する前に、まずはそれぞれの制度がどのようなものか、基本的な仕組みを再確認しておきましょう。
① 暦年贈与:毎年コツコツ非課税で渡すシンプルな方法
暦年贈与は、「一年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからない」という制度です。この110万円の基礎控除は、財産をもらう側(受贈者)一人ひとりに対して適用されます。
例えば、父親から110万円、母親から110万円を同じ年にもらうと、合計220万円となり、110万円を超えた部分(110万円)に贈与税がかかります。一方で、父親から長男へ110万円、次男へ110万円を贈与する場合は、もらう側が異なるため、それぞれ非課税となります。
手続きが簡単で、誰から誰への贈与でも使えるため、長年にわたり最もポピュラーな生前贈与の方法として活用されてきました。しかし、この制度には「生前贈与加算」という重要なルールがあり、これが今回の税制改正で大きく変更されたポイントです。
② 相続時精算課税制度:まとまった額を非課税で渡し、相続時に精算する方法
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫へ贈与を行う場合に選択できる制度です。
この制度を選択すると、合計2,500万円までの贈与が非課税となる特別な控除枠を利用できます。2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。
ただし、その名の通り「相続時に精算」する仕組みであり、この制度を使って贈与した財産は、贈与した人が亡くなった際に、すべて相続財産に足し戻して相続税を計算します。その際、すでに支払った贈与税があれば、計算された相続税額から差し引くことができます。
つまり、本質的には「贈与税を相続税として先送りする制度」であり、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年贈与に戻ることはできません。
【2025年最新】税制改正による3つの大きな変更点
2024年1月1日から施行された税制改正は、この2つの制度の使い勝手と損得勘定を劇的に変えました。2025年現在の贈与を考える上で、絶対に知っておくべき3つのポイントを解説します。
変更点1:暦年贈与の「生前贈与加算」が3年から7年に延長
暦年贈与の最大の注意点である「生前贈与加算(相続財産への持ち戻し)」の期間が、大幅に延長されました。
これは、贈与者が亡くなった際、亡くなる前一定期間内に行われた贈与は「なかったこと」にして、相続財産に足し戻して相続税を計算するというルールです。
【改正前】相続開始前3年以内の贈与が対象
【改正後】相続開始前7年以内の贈与が対象
これにより、例えば2025年に贈与を行っても、万が一2032年までに相続が発生すると、その贈与額は相続財産に加算されてしまいます。暦年贈与による相続税対策の効果が、以前よりも薄れてしまったと言えます。
(※注)延長された4年分(相続開始前3年超~7年以内)の贈与については、その合計額から100万円を控除した金額が持ち戻しの対象となります。
変更点2:相続時精算課税制度に「年間110万円の基礎控除」が新設
今回の改正で最も注目すべき変更点です。これまで使い勝手が悪いとされてきた相続時精算課税制度が、非常に魅力的な制度に生まれ変わりました。
具体的には、相続時精算課税制度を選択した場合でも、従来の2,500万円の特別控除とは別に、新たに毎年110万円の基礎控除枠が創設されました。
そして、この新しい年間110万円の基礎控除を使って贈与された財産は、相続時に遺産に持ち戻す必要がありません(生前贈与加算の対象外)。
つまり、相続時精算課税制度を選択すれば、7年以内の死亡といったリスクを気にすることなく、毎年110万円ずつ確実に相続財産を減らしていくことが可能になったのです。これは非常に大きなメリットです。
変更点3:贈与財産が災害で被害を受けた場合の再計算
少し細かい点ですが、相続時精算課税制度のリスクを軽減する改正も行われました。この制度で家や土地などの不動産を贈与した場合、相続時の評価額は「贈与時の価額」で固定されます。しかし、贈与後に地震や水害などでその不動産が被害を受けた場合、価値が下がっているにもかかわらず高い贈与時の価額で相続税が計算されるという問題がありました。改正により、そうした場合は被害額を控除して再計算できるようになり、より安心して利用できるようになりました。
結局どっちがお得?ケース別・おすすめの選択
改正後のポイントを踏まえ、どのような人がどちらの制度に向いているのかを整理しました。
暦年贈与がおすすめなケース
- 多くの人に幅広く贈与したい方
110万円の基礎控除はもらう側(受贈者)ごとの制度です。子ども2人、孫4人の合計6人に毎年110万円ずつ贈与するなど、多人数に財産を分散したい場合は、暦年贈与が有効です。 - 相続税がかからない見込みの方
遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回ることが明らかな方は、そもそも相続税対策を深く考える必要がありません。シンプルな暦年贈与で十分でしょう。 - 健康で、長期間にわたる計画的な贈与が可能な方
7年の持ち戻し期間は確かに長くなりましたが、15年、20年といった長期的なスパンでコツコツ贈与を続けられるのであれば、暦年贈与は依然として有効な手段です。
相続時精算課税制度がおすすめなケース
- 相続税の課税が確実な富裕層の方
新設された年間110万円の非課税枠は、持ち戻しが一切不要です。相続税率が高い方ほど、この枠を使って毎年確実に相続財産を減らしていくメリットは計り知れません。 - 収益物件や値上がり期待の資産を贈与したい方
相続時に評価されるのは「贈与時の価額」です。家賃収入を生むアパートや、将来値上がりが期待できる株式などを早めに贈与しておけば、相続時の評価額の上昇を抑えることができます。 - 子や孫の住宅購入資金など、すぐにまとまった額を援助したい方
2,500万円の特別控除枠を使えば、一度に大きな金額を非課税で贈与できます。(※住宅取得等資金贈与の非課税制度との併用も要検討) - 高齢になってから生前贈与を考え始めた方
「7年ルール」を気にすることなく、確実に年間110万円の非課税贈与ができるため、高齢の方にとって非常に使いやすい制度になりました。
まとめ:生前贈与の計画は専門家への相談が不可欠
2025年現在、生前贈与の選択肢は税制改正によって大きく変わりました。特に「相続時精算課税制度」の使い勝手が劇的に向上し、これまで暦年贈与一択だった方々にとっても、有力な選択肢となったことは間違いありません。
しかし、どちらの制度が最適かは、あなたの資産状況、家族構成、年齢、健康状態、そしてどのような財産を渡したいかによって全く異なります。一度選択すると元に戻せないケースもあるため、自己判断は禁物です。
生前贈与は、家族の未来を豊かにするための素晴らしい手段ですが、一歩間違えれば、かえって税金の負担を増やしたり、家族間のトラブルの原因になったりもします。ご自身の状況に最も合った方法を選択するために、まずは一度、税理士などの専門家に相談し、最適な贈与プランを設計することをお勧めします。
-
前の記事

性格の不一致による税理士変更を防ぐために有効な方法とは? 2025.05.11
-
次の記事

青色申告と白色申告の違い・節税効果やメリットを徹底比較 2025.07.20