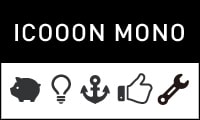インボイス登録したら何をすべき?請求書の発行から経理処理の変更点まで徹底ガイド
- 2023.10.02
- 税金・法律
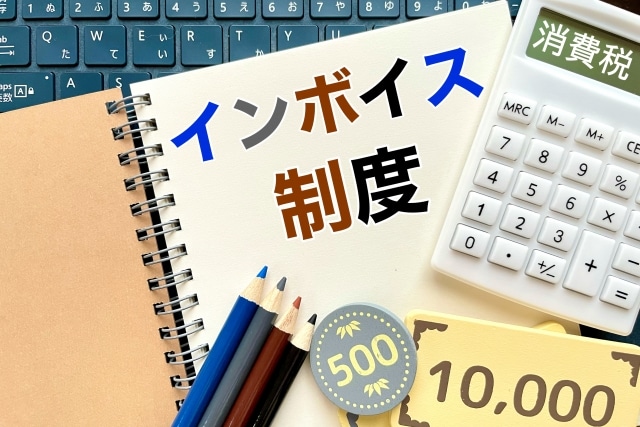
「ようやくインボイス(適格請求書発行事業者)の登録が完了し、税務署から登録番号の通知が届いた!でも、正直なところ、今日から具体的に何をどう変えればいいのか、よくわかっていない…」
多くの個人事業主や中小企業の経営者の方が、今まさにこのような状況にいらっしゃるのではないでしょうか。インボイス制度への登録はゴールではなく、あくまでスタートです。本当の対応は、登録後の日々の業務フローを、制度のルールに合わせて正しく変更していくことにあります。
請求書のフォーマットは?取引先には何を連絡すればいい?経理のやり方はどう変わるの?そんな疑問や不安を解消するため、この記事ではインボイス登録後に「やるべきこと」を徹底的にガイドします。請求書の発行(売上)から、経費の処理(仕入)まで、具体的な変更点をステップバイステップでわかりやすく解説しますので、ぜひ日々の業務のチェックリストとしてご活用ください。
まず最初にやるべき3つのこと
インボイスの登録番号を受け取ったら、まずは以下の3つのアクションを速やかに行いましょう。これがスムーズな制度対応の第一歩です。
① 取引先への登録番号の通知と請求書フォーマット変更の連絡
最も重要なのが、あなたの登録を待っていた取引先(買い手側)への連絡です。取引先は、あなたの登録番号が記載された請求書(インボイス)を受け取らないと、消費税の仕入税額控除ができません。つまり、取引先の納税額に直接影響するのです。
以下の内容を記載したメールなどで、主要な取引先には速やかに通知しましょう。
- 適格請求書発行事業者の登録が完了した旨
- 自社の登録番号(T+13桁の番号)
- いつから請求書のフォーマットがインボイス対応のものに切り替わるか
この一手間が、取引先からの問い合わせを防ぎ、信頼関係を維持する上で非常に重要になります。
② 請求書・領収書フォーマットの変更
今まで使っていた請求書や領収書のテンプレートは、そのままではインボイスとして認められません。必ず以下の項目が記載された新しいフォーマットに変更する必要があります。
【適格請求書に必要な6つの記載事項】
- 発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
特に太字で示した「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の3つが、従来の請求書からの主な変更点です。10%対象と8%対象の商品が混在する場合は、それぞれを明確に区分して記載する必要があります。
③ 会計ソフトの設定確認・アップデート
freeeやマネーフォワード クラウドといったクラウド会計ソフトを利用している場合、制度対応は比較的スムーズです。しかし、自動では切り替わらない設定項目もあるため、必ず確認しましょう。
- 事業者の設定画面で、自社の登録番号を正しく入力する。
- 請求書作成機能のテンプレートが、インボイス対応のフォーマットに設定されているか確認する。
- 経費などを入力する際の税区分の設定で、インボイスを受け取った取引かどうかを区別できる設定が追加されていることを確認する。
これらの初期設定を済ませておけば、日々の業務が格段に楽になります。
日々の経理業務はどう変わる?【売上・請求編】
インボイス発行事業者になったことで、売上や請求に関する業務には新たな義務が発生します。
「適格請求書(インボイス)」の発行義務
課税事業者である取引先からインボイスの発行を求められた場合、正当な理由なく交付を拒否することはできません。これは法律上の義務となります。小売業や飲食業、タクシー業など、不特定多数の顧客を相手にする事業の場合は、記載事項を一部省略した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています。
値引き・返品があった場合の「適格返還請求書」
売上の値引きや返品、割戻しなどがあり、買主へ返金を行う場合には、「適格返還請求書(返還インボイス)」を発行する義務が生じます。これは、マイナス分のインボイスと考えると分かりやすいでしょう。返還インボイスにも登録番号や、値引きの対象となった取引の内容などを記載する必要があります。
発行した請求書の「控え」の保存義務
発行したインボイス(適格請求書、簡易インボイス、返還インボイス)は、その写しを7年間保存することが義務付けられています。紙で発行した場合でも、PDFなどの電子データで保存しておけば問題ありません。電子帳簿保存法の観点からも、請求書の発行から保存までを一貫してデータで行う「電子インボイス」への移行を検討するのがおすすめです。
日々の経理業務はどう変わる?【仕入・経費編】
インボイス制度で最も大きな影響を受けるのが、仕入や経費の処理です。ここを正しく理解しないと、自分が納める消費税額で損をしてしまう可能性があります。
受け取った請求書が「インボイス」か必ず確認する
仕入税額控除(支払った消費税分を、預かった消費税から差し引くこと)を適用するためには、原則として、取引相手から交付された「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。
したがって、今後は受け取った請求書やレシートがインボイスの要件を満たしているか、以下の点を確認する作業が毎回発生します。
- 相手の登録番号(T+13桁)が記載されているか?
- 消費税額が税率ごと(10%, 8%)に区分して記載されているか?
- その他、必要な項目がすべて記載されているか?
相手が本当に登録事業者か疑わしい場合は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索して確認できます。
帳簿の付け方の変更点
インボイス制度の開始に伴い、帳簿の付け方も変わります。具体的には、仕入税額控除の対象となる取引かどうかを、帳簿上で明確に区別して記録する必要があります。
会計ソフトでは、同じ10%の経費でも、「課税仕入10%(インボイス有り)」と「課税仕入10%(インボイス無し・経過措置80%控除対象)」のように、税区分が細分化されています。受け取った請求書の種類に応じて、正しい税区分を選択して入力する作業が重要になります。
免税事業者からの仕入がある場合の「経過措置」
これまで取引のあった免税事業者がインボイス登録をしなかった場合、その相手からの仕入は、原則として仕入税額控除ができなくなります。しかし、急激な負担を緩和するため、期間限定の「経過措置」が設けられています。
- 2026年9月30日まで:免税事業者からの仕入でも、消費税相当額の80%は控除可能
- 2029年9月30日まで:免税事業者からの仕入でも、消費税相当額の50%は控除可能
この経過措置を適用するためには、帳簿に「80%控除対象」などのように、経過措置の対象である旨を記載する必要があります。
まとめ:インボイス登録はスタート地点。適切な運用で信頼を築こう
インボイス制度への登録は、あくまで制度に対応するためのスタートラインに立ったに過ぎません。その後の実務、特に「①取引先への通知」「②請求書フォーマットの変更」「③日々の経理処理の変更」を正確に運用していくことが、事業者には求められます。
一見すると、業務の負担が増える面倒な制度に感じるかもしれません。しかし、インボイスを正確に発行し、受け取ったインボイスを適切に処理することは、取引先との円滑な関係を維持し、自社の税務コンプライアンスを示す上で不可欠です。それは、事業の信頼性を高めることにも繋がります。
まずは本記事で解説した「やるべきこと」を一つひとつ確実にこなし、新しい経理のルールに慣れていきましょう。もし運用に不安があれば、税理士などの専門家に相談し、自社の業務フローを再点検することをお勧めします。
-
前の記事

税理士を目指す上で知っておきたい求人の探し方 2023.09.25
-
次の記事

遺産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討 2023.11.15