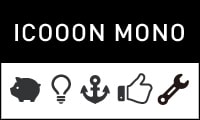減価償却とは?仕組みをわかりやすく解説!節税効果と中古資産を購入するメリット
- 2025.03.18
- 税金・法律
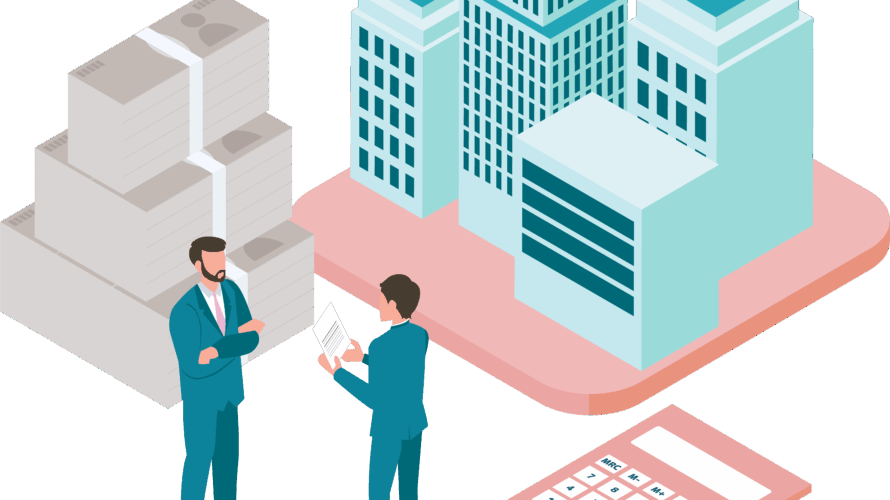
事業を運営していると、「減価償却(げんかしょうきゃく)」という言葉を耳にする機会は多いでしょう。しかし、「言葉は知っているけれど、意味はよくわからない」「高価なパソコンや車を買ったけど、どうやって経費にすればいいの?」と、その複雑なイメージに苦手意識を持っている方も少なくないかもしれません。
実は、この減価償却は、単なる会計上の難しいルールではありません。その仕組みを正しく理解することで、手元に残るキャッシュを最大化し、効果的な節税を実現するための強力な武器となるのです。
この記事では、一見とっつきにくい減価償却の基本から、具体的な計算方法、そして大きな節税効果が期待できる「中古資産」の活用法まで、専門用語をできるだけ使わずに、わかりやすく解説していきます。減価償却を味方につけて、賢い設備投資と税金対策を実現しましょう。
そもそも減価償却とは?時間の経過で価値が減るという考え方
まずは、減価償却という考え方の根本を理解することから始めましょう。
減価償却の基本的な仕組み
あなたが事業のために100万円の機械を購入したとします。この100万円を、購入したその年に全額経費として計上するとどうなるでしょうか。その年は100万円の費用が発生して利益が大幅に減るか、赤字になるかもしれません。そして翌年以降は、その機械が稼働して売上に貢献しているにもかかわらず、関連する費用はゼロになってしまいます。これでは、各年の正しい経営成績を表しているとは言えません。
そこで登場するのが「減価償却」という考え方です。
減価償却とは、パソコン、車、機械といった高額な固定資産の購入費用を、一度に経費にするのではなく、その資産が使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して、少しずつ経費として計上していく会計上のルールです。
つまり、「資産の価値は、時間の経過や使用によって少しずつ減っていく」と考え、その価値の減少分を毎年「減価償却費」という経費として計上していくのです。これにより、資産が売上に貢献する期間と、その費用を対応させることができ、より正確な業績を把握できるようになります。
減価償却の対象になる資産・ならない資産
すべての資産が減価償却の対象になるわけではありません。対象となる資産には、以下の3つの条件があります。
- 時の経過や使用により価値が減少するもの
- 事業のために使用しているもの
- 取得価額が10万円以上のもの
【対象になる資産の例】
- 建物:事務所、店舗、工場、倉庫など
- 機械装置:製造機械、業務用クレーンなど
- 車両運搬具:営業車、トラックなど
- 工具器具備品:パソコン、コピー機、応接セット、エアコンなど
【対象にならない資産の例】
- 土地、骨董品、美術品:これらは時間の経過によって価値が減少しない(むしろ価値が上がる可能性もある)ため、減価償却の対象外です。
- 棚卸資産:販売目的で保有している商品や製品は対象外です。
- 取得価額が10万円未満の資産:「消耗品費」などの科目で、購入した年に全額を経費として計上します。
減価償却費の計算方法【定額法と定率法】
減価償却費を計算するには、主に「取得価額」「耐用年数」「償却方法」の3つの要素が必要です。ここでは、代表的な償却方法である「定額法」と「定率法」について解説します。
毎年、同じ額を償却する「定額法」
定額法は、毎年同じ金額の減価償却費を計上していく、最もシンプルな計算方法です。個人事業主の場合は、特に届出をしない限り、この定額法が適用されます。
計算式: 取得価額 × 定額法の償却率
※償却率は、資産の耐用年数に応じて法律で定められています。
【計算例】50万円のパソコン(耐用年数4年、償却率0.250)を購入した場合
50万円 × 0.250 = 12.5万円
毎年12.5万円ずつ、4年間にわたって経費として計上していきます。計算が簡単で、毎年の利益計画が立てやすいのがメリットです。
初年度に多く償却する「定率法」
定率法は、購入した初年度に最も多くの減価償却費を計上し、年々その金額が減少していく計算方法です。法人の場合は、原則としてこの定率法が適用されます(建物などを除く)。
計算式: (取得価額 - 前年までの減価償却費累計額) × 定率法の償却率
【計算例】50万円のパソコン(耐用年数4年、償却率0.500)を購入した場合
- 1年目:50万円 × 0.500 = 25万円
- 2年目:(50万円 - 25万円) × 0.500 = 12.5万円
- 3年目:(50万円 - 37.5万円) × 0.500 = 6.25万円 → 償却保証額を下回るため計算方法が変わりますが、年々減少していくイメージです。
購入初期に多くの経費を計上できるため、初年度の税負担を大きく軽減できるというメリットがあります。
減価償却の節税効果と特例制度
減価償却は、利益を計算する上で経費を計上するルールですが、これがなぜ節税につながるのでしょうか。
減価償却が節税になる仕組み
税金(所得税や法人税)は、事業の利益(売上 - 経費)に対して課税されます。つまり、経費が多ければ多いほど、課税対象となる利益は圧縮され、結果として納める税金は少なくなります。
減価償却の最大のポイントは、「現金支出を伴わない経費」であるという点です。資産を購入した年に現金は支払済みですが、その後、耐用年数にわたって「減価償却費」という経費を計上し続けることができます。これにより、実際のキャッシュアウトはないのに、帳簿上の利益を減らして節税することが可能になるのです。
【青色申告者向け】知って得する特例制度
特に青色申告を行っている個人事業主や中小企業は、さらに有利な特例制度を利用できます。
少額減価償却資産の特例
これは非常に強力な制度で、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、購入・使用を開始した年に全額を経費として計上できるというものです(年間合計300万円まで)。
(例)28万円の高性能パソコンを購入した場合
通常の減価償却(定額法)であれば、4年間にわたって7万円ずつ経費計上します。しかし、この特例を使えば、購入した年に28万円全額を一括で経費にできます。これにより、その年の利益を大幅に圧縮し、納税額を大きく減らすことができるのです。
【大きな節税メリット】中古資産を購入する賢い選択
減価償却の仕組みを応用すると、「中古資産」の購入が非常に有効な節税策となることがあります。
なぜ中古資産は節税に有利なのか?
結論から言うと、中古資産は、新品に比べて法定耐用年数を短く設定できるため、購入費用をより短期間で経費化できるからです。
減価償却は、耐用年数が短ければ短いほど、1年あたりの経費計上額は大きくなります。中古資産は、すでに他の人によって使用されてきた分、新品よりも短い期間で価値がなくなると考えられるため、耐用年数を短縮することが認められているのです。
中古資産の耐用年数の計算方法
中古資産の耐用年数は、簡便法という計算式で算出します。
- 法定耐用年数をすべて経過している場合:
法定耐用年数 × 20% (計算結果の1年未満の端数は切り捨て) - 法定耐用年数の一部を経過している場合:
(法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 × 20%)
具体例:中古の高級車が節税に使われる理由
この仕組みを利用した有名な節税方法に、中古の高級車の購入があります。
【例】4年落ちの中古車(新車時の法定耐用年数6年)を400万円で購入した場合
この場合、経過年数が法定耐用年数の一部(4年)なので、簡便法で耐用年数を計算します。
(法定耐用年数6年 - 経過年数4年) + (経過年数4年 × 20%) = 2年 + 0.8年 = 2.8年
→ 1年未満の端数は切り捨てるため、耐用年数は2年となります。
400万円の資産を、新品の6年ではなく、わずか2年で償却できるのです。定率法(2年耐用の場合、償却率1.000)を適用すれば、購入した初年度に400万円のほぼ全額を減価償却費として経費に計上することが可能です。これにより、その年に大きな利益が出ている場合でも、利益を大幅に圧縮して納税額を抑えることができます。
もちろん、これはあくまで事業に必要な車であることが大前提であり、個人的な使用目的では認められません。しかし、この仕組みを知っているかどうかで、設備投資の戦略は大きく変わってきます。
まとめ:減価償却を理解して、賢い設備投資と節税を
今回は、減価償却の基本的な仕組みから、節税効果、そして中古資産を活用した応用テクニックまでを解説しました。
減価償却は、単に帳簿をつけるためのルールではありません。いつ、どのような資産に、いくら投資するべきかという経営判断と、それに伴う納税計画を立てる上で、非常に重要な戦略ツールです。特に、30万円未満の少額減価償却資産の特例や、中古資産の短い耐用年数を活用することは、キャッシュフローを改善し、事業の成長を加速させる上で大きな力となります。
高額な設備投資を検討する際には、ぜひ本記事の内容を思い出してください。そして、どの方法が自社にとって最も有利になるか判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談し、事業の状況に合わせた最適なアドバイスを受けることをお勧めします。
-
前の記事

【2025年版】ふるさと納税の仕組みとは?上限額の計算方法と確定申告(ワンストップ特例)のポイント 2025.02.17
-
次の記事

飲食代は会議費?それとも交際費?税務調査で指摘されないための明確な分け方と上限額 2025.04.12