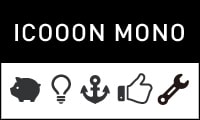【中小企業経営者向け】決算前に見直したい!今すぐできる王道の法人税節税策10選
- 2024.11.02
- 税金・法律

企業の経営者様にとって、決算は一年間の事業活動の成果を総括する重要な時期です。特に、利益が大きく出た年度には、いかにして法人税の負担を軽減するかが大きな課題となります。法人税の節税は、単に税金を安くすることだけでなく、手元に残る資金を増やし、企業の成長に再投資するための重要な経営戦略の一つです。
この記事では、決算間近の中小企業経営者様が、今すぐ取り組むべき王道かつ効果的な法人税の節税策を10選に絞ってご紹介します。税務の専門家である税理士の視点から、合法的にかつ確実に税負担を軽減するための具体的な方法を解説します。
1. 経費の計上漏れがないか徹底的にチェックする
決算の最終段階で、最もシンプルかつ効果的な節税策が「経費の計上漏れ」をなくすことです。領収書や請求書、レシートなどを再度見直し、事業に関係する支出でまだ経費として処理していないものがないか確認しましょう。
具体的には、以下のような項目を見落としがちです。
- 消耗品費(文房具、事務用品、PC周辺機器など)
- 水道光熱費や通信費(プライベートとの按分計算を忘れていないか)
- 出張旅費や交通費
- 新聞図書費(業務関連の書籍や雑誌の購入費用)
- 会議費や接待交際費
これらの項目を漏れなく計上するだけで、課税所得を減らし、結果的に法人税を減らすことができます。
2. 役員報酬の見直し
役員報酬は、経費として計上できるため、法人税の節税に有効な手段です。しかし、法人税法上、役員報酬には「定期同額給与」というルールがあります。これは、事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、その後は毎月同額を支給するというものです。
決算間際に役員報酬を増額しても、原則として損金(経費)に算入することはできません。ただし、期首から3ヶ月以内の見直しであれば、節税のチャンスが生まれます。会社の利益状況に応じて、来期の役員報酬額を計画的に見直すことが重要です。
3. 決算賞与の活用
社員に対して支給する「決算賞与」は、従業員のモチベーション向上と法人税の節税を両立できる有効な方法です。決算賞与を損金に算入するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 決算日までに、各従業員への支給額を個別に通知していること
- 通知した金額を、決算日から1ヶ月以内に実際に支払うこと
- 通知した金額を、経費として帳簿に記載していること
特に、決算直前に利益が出ていることが判明した際に、有効な節税策となります。
4. 従業員の福利厚生の充実
従業員の福利厚生にかかる費用は、原則として全額経費として計上できます。社員旅行や忘年会、歓送迎会などの費用は、「会議費」や「福利厚生費」として処理が可能です。
ただし、過度に高額な費用や、特定の役員のみが恩恵を受けるような費用は、経費として認められない場合があります。福利厚生費として認められるためには、「社会通念上妥当な範囲内」であることと、「すべての従業員が対象」であることが重要です。
5. 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
「中小企業倒産防止共済」は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐことを目的とした共済制度です。この共済に加入して掛金を支払うことで、その掛金の全額を経費として計上することができます。
- 掛金:月額5,000円から20万円まで、5,000円単位で設定可能
- 前納:1年分の掛金を前納することができ、その全額を一括で経費計上できる
- 限度額:掛金の総額は800万円まで
節税効果が高く、将来の経営リスクにも備えられるため、多くの経営者が利用している王道的な節税策です。
6. 小規模企業共済
「小規模企業共済」は、経営者の退職金制度です。個人事業主や会社の役員が加入でき、毎月の掛金は全額が所得控除の対象となります。法人税の節税ではなく、役員個人の所得税・住民税の節税になりますが、役員報酬を経費として計上している法人にとっては、実質的な節税効果があります。
7. 設備投資による節税
「中小企業投資促進税制」や「中小企業経営強化税制」など、中小企業向けの設備投資を促すための優遇税制が存在します。
- 中小企業投資促進税制:一定の条件を満たす機械装置、ソフトウェアなどを取得した場合、取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除のいずれかを選択適用できます。
- 中小企業経営強化税制:指定された設備を取得した場合、即時償却、または税額控除を選択適用できます。
これらの制度を活用すれば、多額の設備投資費用を一括で経費として計上できるため、大きな節税効果が期待できます。ただし、適用には細かな要件がありますので、事前に税理士に相談することをお勧めします。
8. 決算時期の変更
事業年度を自由に設定できることも、中小企業にとっての強みです。もし特定の月に大きな利益が出ることがわかっている場合、その時期を事業年度の開始月に設定することで、利益が集中する時期を分散し、計画的に節税策を実行する時間を確保できます。
ただし、一度変更すると再度変更するには一定の制約があるため、慎重な検討が必要です。
9. 不良在庫の処分
決算期末に抱えている「不良在庫」は、資産として計上されているため、課税対象となります。しかし、適切な手続きを踏むことで、評価損を計上し、経費にすることができます。
不良在庫の判断基準は、「陳腐化している」「破損している」「有効期限切れ」などです。税務上認められるためには、その在庫が「将来販売不能」または「価値が著しく低下」していることを客観的に証明する必要があります。
10. 税理士への相談
最後に、最も重要かつ確実な節税策が「税理士に相談すること」です。
税法は常に改正されており、自社だけで最新の情報を把握し、最適な節税策を講じることは非常に困難です。税理士は、お客様の会社の事業内容や財務状況を正確に把握した上で、合法的にかつ効果的な節税策を提案することができます。
また、単なる節税だけでなく、企業のキャッシュフロー改善や資金繰り、経営全般に関するアドバイスも提供できます。
まとめ
法人税の節税は、会社の利益を最大化し、将来への投資に繋げるための重要な経営活動です。今回ご紹介した10の節税策は、どれも合法的に税負担を軽減できる王道的な方法です。
決算間際になって慌てることのないよう、日頃から計画的に会計処理を行い、節税のチャンスを最大限に活かしましょう。ただし、行き過ぎた節税は、会社の資金繰りを悪化させるリスクも伴います。
当会計事務所では、お客様の状況に合わせた最適な節税プランをご提案しています。ご不安な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。専門家として、お客様の経営を強力にサポートさせていただきます。
-
前の記事

【個人事業主必見】どこまで経費で落ちる?家賃・光熱費・飲食代など具体例で解説 2024.10.17
-
次の記事

医療費控除で税金はいくら戻る?対象費用と申請方法、家族分をまとめる際の注意点 2024.12.10