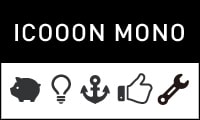【2025年版】ふるさと納税の仕組みとは?上限額の計算方法と確定申告(ワンストップ特例)のポイント
- 2025.02.17
- 税金・法律

「ふるさと納税」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その仕組みやメリットを正しく理解されているでしょうか?「興味はあるけれど、手続きが難しそう」「本当に節税になるの?」といった疑問を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすることで、寄附金のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される制度です。さらに、寄附のお礼として各地の特産品がもらえるため、実質2,000円の自己負担で全国の美味しいものや魅力的な品を手に入れることができます。
しかし、控除される金額には上限があり、その計算方法や、控除を受けるための手続き(確定申告またはワンストップ特例制度)を正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、2025年(令和7年)のふるさと納税制度について、その基本的な仕組みから、ご自身の収入や家族構成に応じた控除上限額の計算方法、そして寄附金控除を受けるための手続きについて、分かりやすく解説します。ふるさと納税をこれから始めてみたい方、すでに利用しているけれど改めて仕組みを確認したい方は、ぜひご一読ください。
ふるさと納税の基本的な仕組み
ふるさと納税は、地方創生を目的とした寄附金控除制度です。自分の生まれ故郷や、応援したい自治体に寄附をすることで、税金の控除が受けられます。
ふるさと納税で税金が安くなる仕組み
ふるさと納税の最大の魅力は、実質2,000円の自己負担で、豪華な返礼品を受け取れる点です。これは、寄附した金額から2,000円を差し引いた金額が、所得税と住民税から控除される仕組みになっているためです。
たとえば、年収500万円の独身の方が30,000円をふるさと納税で寄附した場合を考えてみましょう。
- 30,000円(寄附金額) – 2,000円(自己負担額) = 28,000円
この28,000円が、所得税と住民税から控除されます。
所得税からの控除
所得税からの控除額は、(ふるさと納税額 – 2,000円)× 所得税率で計算されます。
上記の例では、28,000円が所得税の課税所得から控除されることで、所得税が安くなります。
住民税からの控除
住民税からの控除は、「基本控除額」と「特例控除額」の2つで構成されます。
- 基本控除額:(ふるさと納税額 – 2,000円)× 10%
- 特例控除額:(ふるさと納税額 – 2,000円)×(90% – 所得税率)
上記の例では、28,000円が住民税の基本控除額と特例控除額として控除され、翌年の住民税が安くなります。
このように、所得税からの還付(確定申告の場合)と、翌年の住民税からの控除によって、実質的な自己負担額が2,000円になるという仕組みです。
控除の対象となるふるさと納税額の上限
ふるさと納税で控除を受けられる金額には、上限が定められています。この上限額は、寄附者の年収(所得)、家族構成、その他の控除(住宅ローン控除、医療費控除など)によって異なります。
上限額を超えて寄附した分は、控除の対象とならず、全額が自己負担となりますので注意が必要です。
ふるさと納税のサイトでは、簡単な質問に答えるだけで上限額をシミュレーションできるツールが提供されていますので、ご自身の状況を把握する上で活用することをおすすめします。
【2025年版】ふるさと納税の上限額の計算方法
ふるさと納税を賢く利用するためには、ご自身の控除上限額を正確に把握することが最も重要です。ここでは、基本的な計算方法を解説します。
上限額を決定する主な要因
ふるさと納税の控除上限額は、以下の要因によって変動します。
- 所得:年収が高いほど、所得税・住民税の納税額が多いため、控除上限額も高くなります。
- 家族構成(扶養親族の有無):配偶者や扶養家族がいる場合、所得控除が増えるため、その分、ふるさと納税の控除上限額は低くなります。
- その他の所得控除:住宅ローン控除、iDeCoや生命保険料控除、医療費控除などを利用している場合、課税所得が減少するため、ふるさと納税の控除上限額も低くなります。
具体的な計算方法
ふるさと納税の控除上限額は、住民税の「特例控除」の上限によって決まります。特例控除額は、住民税所得割額の20%が上限と定められています。
計算式
(住民税所得割額 × 20%) / (90% – 所得税率) + 2,000円
所得税率
所得税率は、課税所得に応じて以下の通りに定められています。
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
例)年収500万円、独身、社会保険料控除が70万円の場合
課税所得を計算
500万円 – 103万円(給与所得控除) – 48万円(基礎控除) – 70万円(社会保険料控除) = 279万円
※2025年時点の所得控除額は変更の可能性があります。
所得税率を確認
課税所得279万円は、所得税率10%に該当します。
住民税所得割額を計算
住民税所得割額は、一般的に課税所得の10%です。
279万円 × 10% = 27.9万円
ふるさと納税の上限額を計算
(27.9万円 × 20%) / (90% – 10%) + 2,000円
= 5.58万円 / 0.8 + 2,000円
= 69,750円 + 2,000円
= 71,750円
この例の場合、上限額は約71,750円となります。ただし、正確な上限額は、年間の収入や控除額が確定しないと算出できません。年末調整や確定申告を終えた後で、源泉徴収票や確定申告書を確認して計算することが最も正確です。
ふるさと納税の控除を受けるための手続き
ふるさと納税で寄附金控除を受けるためには、「確定申告」または「ワンストップ特例制度」のいずれかの手続きが必要です。
確定申告
確定申告は、年間の所得とそれに対する所得税額を計算し、税務署に申告する手続きです。以下に該当する方は、ワンストップ特例制度を利用できないため、確定申告を行う必要があります。
- 給与所得者で、年間2,000万円を超える収入がある方
- 2か所以上の会社から給与を受け取っている方
- 副業の所得が20万円を超える方
- 医療費控除や住宅ローン控除など、ふるさと納税以外の控除も申告する方
確定申告の手順
「寄附金受領証明書」を保管する
寄附を行った自治体から郵送される「寄附金受領証明書」は、確定申告で必要となる重要な書類です。紛失しないように保管しておきましょう。最近では、寄附サイトから発行される電子データで代用できる場合もあります。
確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力するだけで簡単に申告書を作成できます。
税務署に提出する
作成した確定申告書を、所轄の税務署に提出します。e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅から提出できるため便利です。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要となる簡便な制度です。この制度を利用するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- もともと確定申告の必要がない給与所得者であること
- ふるさと納税の寄附先が年間5自治体以内であること
ワンストップ特例制度の手順
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を準備する
ふるさと納税を申し込む際に、「ワンストップ特例制度の利用を希望する」にチェックを入れると、寄附した自治体からこの申請書が送付されます。
必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添付する
申請書に住所や氏名などを記入し、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付します。
寄附した自治体へ郵送する
寄附した年の翌年1月10日までに、寄附先の自治体に必着するように郵送します。この期限を過ぎてしまうと、ワンストップ特例制度は利用できなくなり、確定申告が必要となりますので注意しましょう。
最後に
ふるさと納税は、税金の控除を受けながら、応援したい自治体に貢献し、魅力的な返礼品を楽しめる素晴らしい制度です。しかし、控除上限額の計算や、正しい手続きを行わないと、実質的な自己負担が増えてしまう可能性もあります。
特に、住宅ローン控除や医療費控除、生命保険料控除など、他の控除も利用されている方は、ご自身の正確な上限額を把握しておくことが重要です。
もし、ご自身の控除上限額の計算や、確定申告の手続きについてご不安な点がございましたら、お気軽に当会計事務所までご相談ください。専門家である税理士が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、ふるさと納税を最大限に活用できるようサポートさせていただきます。
ふるさと納税を賢く活用し、豊かな暮らしを実現するための一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?
-
前の記事

役員報酬はいくらが最適?法人税と社会保険料を抑える上手な設定方法とシミュレーション 2025.01.12
-
次の記事
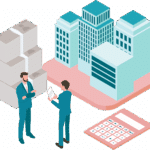
減価償却とは?仕組みをわかりやすく解説!節税効果と中古資産を購入するメリット 2025.03.18