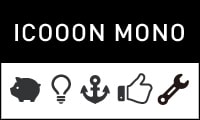医療費控除で税金はいくら戻る?対象費用と申請方法、家族分をまとめる際の注意点
- 2024.12.10
- 税金・法律

「去年は家族の入院や通院が重なって、医療費がたくさんかかったな…」
「出産費用って、税金が戻ってくるって本当?」
「ドラッグストアで買った薬も対象になるの?」
1年を振り返ったとき、家計における医療費の負担は決して小さくないものです。そんな時にぜひ活用したいのが、「医療費控除」という制度です。
医療費控除は、納めすぎた税金が「還付金」として手元に戻ってくる、とてもありがたい制度ですが、会社員の方でも年末調整では手続きができず、自分で確定申告をする必要があります。「手続きが面倒くさそう」と感じて、利用を諦めてしまっている方も多いのではないでしょうか。
しかし、その仕組みや対象となる費用を正しく理解すれば、手続きは決して難しいものではありません。この記事では、医療費控除の基本から、皆さんが最も気になる「いくら戻ってくるのか」という計算方法、対象となる費用の具体例、そして申請方法までを、一つひとつ丁寧に解説していきます。知っているのと知らないのとでは大違い。この記事を読んで、払いすぎた税金をしっかり取り戻しましょう。
そもそも医療費控除とは?知らないと損する制度の仕組み
まずは、医療費控除がどのような制度なのか、基本的な仕組みを理解しましょう。
医療費控除の基本
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、自分自身や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得からその金額を差し引くことができる「所得控除」の一種です。
「所得控除」という言葉が少し難しいかもしれませんが、これは「課税対象となる所得金額を減らすことができる仕組み」と考えてください。課税対象の所得が減ることで、結果として納めるべき所得税や翌年の住民税が安くなる、というわけです。支払った医療費そのものが返ってくるわけではない、という点をまず押さえておきましょう。
医療費控除の対象となる金額は?
「医療費がたくさんかかった」と言っても、支払った全額が控除の対象になるわけではありません。医療費控除額は、以下の計算式で算出します。
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円
ポイントは2つあります。
- 生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などを受け取った場合は、その金額を支払った医療費から差し引く必要があります。
- 原則として、上記の計算後の金額が10万円を超えていなければ、医療費控除は利用できません。
【重要】総所得金額等が200万円未満の方の場合
年間の総所得金額等が200万円未満の場合は、「10万円」の代わりに「総所得金額等の5%」の金額を差し引きます。例えば、所得が180万円の方であれば、180万円 × 5% = 9万円となり、医療費が9万円を超えていれば控除の対象となります。
家族の分も合算できる!「生計を一にする」とは?
医療費控除の最大のポイントは、自分だけでなく、「生計を一にする」家族の医療費もすべて合算して申告できる点です。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。例えば、以下のようなケースも対象となります。
- 単身赴任中のお父さん
- 仕送りをして養っている、実家で暮らす両親
- 学費や生活費を仕送りしている、一人暮らしの大学生の子ども
扶養に入っているかどうかは関係ありません。生活費を共有している実態があればOKです。そして、合算した医療費は、家族の中で最も所得税率が高い(所得が多い)人が代表して申告すると、所得税の還付額が最も大きくなるためお得です。
【いくら戻る?】医療費控除の還付金額シミュレーション
それでは、実際に医療費控除を利用すると、いくら税金が戻ってくるのでしょうか。計算方法とモデルケースを見ていきましょう。
還付金額の計算式
還付される所得税額は、以下の計算式で求められます。
医療費控除額 × あなたの所得税率 = 還付される所得税額
ここで重要なのが「所得税率」です。所得税率は、課税される所得金額に応じて、以下のように段階的に高くなります(累進課税)。
所得税の速算表(令和5年分以降)
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
ご自身の源泉徴収票などで「課税される所得金額」を確認し、税率を当てはめて計算します。
モデルケースで計算してみよう
言葉だけでは分かりにくいので、具体的なモデルケースで見てみましょう。
【モデルケース】
- 申告するAさん:課税所得400万円(所得税率20%)
- 年間の医療費合計(家族分含む):35万円
- 保険金による補てん額:5万円
ステップ1:医療費控除額を計算する
(35万円 - 5万円) - 10万円 = 20万円(医療費控除額)
ステップ2:所得税の還付額を計算する
20万円 × 20%(所得税率) = 4万円
ステップ3:住民税の減額効果も忘れずに!
医療費控除を申請すると、翌年度の住民税も安くなります。住民税の税率は、所得にかかわらず一律10%です。
20万円 × 10%(住民税率) = 2万円
このケースでは、所得税の還付が4万円、翌年度の住民税が2万円安くなるため、合計で6万円もの節税効果があることになります。これは非常に大きいですよね。
【これは対象?】医療費控除の対象になる費用・ならない費用
「この支払いは医療費控除の対象になる?」と迷うことも多いでしょう。基本的な考え方は「治療目的」かどうかです。ここでは、対象になる費用とならない費用の具体例をリストアップします。
医療費控除の対象になる費用の具体例
- 医師、歯科医師による診療費・治療費
- 治療、療養に必要な医薬品の購入費(ドラッグストアで購入した風邪薬や胃薬、湿布薬など)
- 通院のための交通費(電車・バス代が基本。小さな子どもの付き添いも含む)※メモを残しておきましょう
- 緊急時など、やむを得ない場合のタクシー代
- 入院時の部屋代や食事代の自己負担分
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費(腰痛や肩こりの治療など)
- 出産費用(定期健診、検査、通院費、入院費用など)※出産育児一時金は差し引きます
- 子供の歯科矯正(発育段階の不正咬合の治療と認められた場合)
- 介護保険制度のもとで提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 医師の指示による、松葉杖やコルセットなどの購入費用
医療費控除の対象にならない費用の具体例
- 健康診断や人間ドックの費用(※重大な疾病が見つかり、治療に移行した場合は対象になることがあります)
- インフルエンザなどの予防接種の費用
- ビタミン剤やサプリメントなど、健康増進や疲労回復を目的としたものの購入費
- 美容目的の歯科矯正やホワイトニング、審美歯科の費用
- 入院時の差額ベッド代(自己の都合で個室などを希望した場合)
- 実家への里帰り出産のための交通費
- 疲れを癒す目的のリラクゼーションマッサージ
*自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代
医療費控除の申請方法と必要書類
最後に、医療費控除を受けるための具体的な申請手順を解説します。医療費控除は、確定申告によって行います。
ステップ1:必要書類を準備する
まずは以下の書類を準備しましょう。
- 医療費控除の明細書:国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で入手します。
- 医療費の領収書やレシート:明細書を作成するために必要です。申告時に提出する必要はありませんが、自宅で5年間保管する義務があります。
- 保険金などで補てんされた金額がわかる書類(支払通知書など)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合、申告書作成時に必要)
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 還付金を受け取るための金融機関の口座情報
ステップ2:「医療費控除の明細書」を作成する
1年間の医療費の領収書を基に、「医療を受けた人」「病院・薬局などの名称」ごとに支払額をまとめて、「医療費控除の明細書」に記入していきます。
健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」(医療費通知)があれば、その合計額を記入するだけで済むため、明細の記入を大幅に簡略化できます。
ステップ3:確定申告書を作成し、提出する
会社員の方でも、医療費控除を受けるためには必ず確定申告が必要です。作成した「医療費控除の明細書」を添付して、確定申告書を完成させます。
国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで、税額などが自動計算され、簡単に申告書を作成できます。
提出期間は、原則として翌年の2月16日~3月15日ですが、医療費控除のような還付申告の場合は、翌年の1月1日から5年間いつでも提出することができます。忘れていたとしても諦めずに申請しましょう。
まとめ:領収書は1年間保管!諦めずに確定申告を
医療費控除は、自分から能動的に手続きをしない限り、恩恵を受けることができない制度です。日頃から医療費の領収書を封筒などにまとめて保管しておく習慣をつけておくと、確定申告の時期に慌てずに済みます。
「年間10万円もかかっていないだろう」と最初から諦めずに、まずは家族分を合算できないか、対象となる費用に漏れがないかを確認してみてください。出産や入院、歯の治療など、特定の年に大きな支出があった場合は、高確率で対象となる可能性があります。
少しの手間で数万円の税金が戻ってくることも珍しくありません。この記事を参考に、ぜひ医療費控除の申請にチャレンジしてみてください。
-
前の記事

【中小企業経営者向け】決算前に見直したい!今すぐできる王道の法人税節税策10選 2024.11.02
-
次の記事

役員報酬はいくらが最適?法人税と社会保険料を抑える上手な設定方法とシミュレーション 2025.01.12