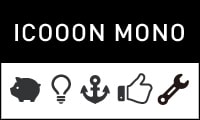【初心者必見】初めての確定申告、いつからいつまで?何が必要?
- 2024.02.17
- 税金・法律

「確定申告」という言葉を聞くと、「何だか難しそう」「自分に関係あるのだろうか」「手続きが面倒くさそう」といったイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に、個人事業主やフリーランスとして独立した方、副業を始めた方、あるいは初めて医療費控除を受けようと考えている方にとって、確定申告は大きなハードルに感じるかもしれません。
しかし、確定申告は決して特別な人だけが行うものではなく、その仕組みを正しく理解すれば、納税は国民の義務であると同時に、払い過ぎた税金を取り戻す権利でもあることがわかります。
この記事では、これまで確定申告に縁がなかった初心者の方を対象に、税理士が専門家の視点から、確定申告の基本の「き」から解説します。「そもそも確定申告って何?」という疑問から、具体的なスケジュール、必要書類、そして申告までの手順まで、この記事を読めば全体像が掴めるように、わかりやすく順を追ってご説明します。
確定申告への不安を解消し、スムーズな第一歩を踏み出すための手助けとなれば幸いです。
そもそも確定申告とは?なぜ必要なの?
まずは、確定申告の基本的な考え方と、どのような人が対象となるのかを理解しましょう。
確定申告とは「税金の精算手続き」のこと
確定申告とは、簡単に言うと**「1年間の所得(儲け)と、それに対する所得税などの税額を自分で計算し、国(税務署)に報告・納税する一連の手続き」**のことです。
対象となるのは、毎年1月1日から12月31日までの1年間です。この期間の収入から必要経費などを差し引いて「所得」を算出し、その所得金額に応じて算出された税額と、すでに給与などから天引き(源泉徴収)されている税額などを比較して、最終的な納税額を確定させます。
この精算手続きの結果、算出された税額が源泉徴収額よりも多ければ追加で税金を納付し、逆に源泉徴収額の方が多ければ、払い過ぎた分が還付金として戻ってきます。
確定申告が必要なのはどんな人?
会社員の方の多くは、会社が年末調整で税金の精算を行ってくれるため、個人で確定申告をする必要はありません。しかし、以下のようなケースに当てはまる方は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
- 個人事業主、フリーランス、不動産収入がある方
事業で得た所得や不動産所得がある方は、原則として確定申告が必要です。 - 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
高額所得者の方は、年末調整の対象外となるため確定申告が必要です。 - 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
いわゆる「副業」での所得が20万円を超えた場合がこれに該当します。Webライターやアフィリエイト、配達サービスなどで得た収入が対象です。 - 給与を2か所以上から受けている方
メインの勤務先で年末調整を受けていても、もう一方の勤務先の給与収入と合計して税額を再計算し、確定申告する必要があります。
【2025年版】確定申告の期間はいつからいつまで?スケジュールを徹底解説
確定申告には、申告書の提出と納税にそれぞれ期限が設けられています。期限を過ぎてしまうとペナルティが発生する場合があるため、スケジュールをしっかり把握しておくことが重要です。
申告と納税の原則的な期間
2024年(令和6年)分の所得に関する確定申告の期間は、以下の通りです。
- 申告書の提出期間:2025年(令和7年)2月17日(月)~ 3月17日(月)
- 所得税及び復興特別所得税の納付期限:2025年(令和7年)3月17日(月)
- 消費税及び地方消費税の納付期限:2025年(令和7年)3月31日(月)
原則として、この約1ヶ月の間に申告と納税を完了させる必要があります。例年、期限間近の税務署は大変混雑するため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることを強くおすすめします。
還付申告は1月から提出可能
医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで、払い過ぎた税金の還付を受けるための申告(還付申告)は、2025年(令和7年)1月1日から提出が可能です。対象となる方は、混雑する2月16日以前に手続きを済ませてしまうのがスムーズです。
期限に遅れた場合のペナルティ
が一、正当な理由なく期限内に申告・納税をしなかった場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
- 無申告加算税: 期限内に申告しなかった場合に課される税金。本来納めるべき税額に加え、原則として15%~20%が加算されます。
- 延滞税: 納税が法定納期限に遅れた場合に課される、利息に相当する税金。納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
余計な税金を支払うことがないよう、必ず期限を守りましょう。
確定申告には何が必要?5つのステップで準備しよう
確定申告をスムーズに進めるためには、事前の準備が何よりも大切です。ここでは、申告完了までの流れを5つのステップに分けて解説します。
Step1:申告方法を決める(青色申告 or 白色申告)
個人事業主や不動産所得がある方は、まず「青色申告」と「白色申告」のどちらで申告するかを選択します。
節税メリットを最大限に活かしたいのであれば、断然青色申告がおすすめです。特にe-Tax(電子申告)を利用すれば、最大の65万円控除を受けることができます。
Step2:必要書類を集める
次に、申告書を作成するために必要な書類を収集・整理します。漏れがないようにチェックリストを作成すると良いでしょう。
全員に共通して必要なもの
- 確定申告書:税務署や国税庁のWebサイトから入手できます。
- 本人確認書類:マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード+運転免許証などの身元確認書類。
収入や所得を証明する書類
- 給与所得の源泉徴収票:会社員やアルバイト・パートの方が会社から受け取る書類。
- 公的年金等の源泉徴収票:年金受給者の方に送付される書類。
- 支払調書:フリーランスの方が取引先から受け取ることがある書類。報酬から源泉徴収された金額が記載されています。
経費の証拠となる書類
- 事業に関する経費の領収書やレシート、請求書、クレジットカードの明細など。日付ごと、勘定科目ごとに整理しておきましょう。
各種控除の証明書
- 医療費控除の明細書(病院や薬局の領収書を基に作成)
- 社会保険料(国民年金、国民健康保険)控除証明書
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 寄附金の受領証(ふるさと納税など)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の小規模企業共済等掛金払込証明書
Step3:帳簿を作成し、申告書を作成する
集めた書類を基に、日々の取引を記録した「帳簿」を作成し、その内容を確定申告書に転記していきます。
青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」を作成し、確定申告書に添付します。
近年では、**クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード クラウドなど)**を利用するのが一般的です。銀行口座やクレジットカードと連携すれば、取引データが自動で取り込まれ、簿記の知識がなくても比較的簡単に帳簿付けができます。
申告書の作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利です。画面の案内に従って金額を入力していくだけで、税額が自動計算され、申告書をPDF形式で印刷・保存できます。
Step4:確定申告書を提出する
作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で税務署に提出します。
- e-Tax(電子申告)で提出する
インターネット経由で申告する方法です。24時間いつでも自宅から提出でき、青色申告特別控除65万円の適用要件にもなっています。マイナンバーカードとICカードリーダライタ(または対応スマホ)が必要です。 - 税務署の窓口へ持参または時間外収受箱へ投函する
管轄の税務署へ直接持参します。閉庁後でも「時間外収受箱」に投函すれば提出できます。 - 郵便または信書便で送付する
「信書」として管轄の税務署へ郵送します。通信日付印が提出日とみなされます。
Step5:税金を納付する(または還付を受ける)
申告の結果、納税が必要になった場合は、期限内に以下の方法で納付します。
- 振替納税:指定の金融機関口座から自動で引き落とされる方法。事前に届出が必要です。
- e-Taxで納付:インターネットバンキングなどを利用して電子納付します。
- クレジットカード納付:専用サイトからクレジットカードで納付します。
- QRコードによるコンビニ納付:確定申告書等作成コーナーで発行したQRコードを使い、コンビニで納付します。
- 金融機関または税務署の窓口で現金納付
一方、還付となる場合は、確定申告書に記載した金融機関の口座へ、申告からおよそ1ヶ月~1ヶ月半後に還付金が振り込まれます。
-
前の記事

税理士の変更の大きな理由の一つが「年齢」の問題 2023.12.31
-
次の記事

確定申告が難しいと感じたら?税理士に相談するメリット 2024.03.15